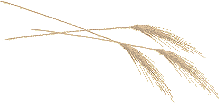 |
洛中洛外の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |
 |
山科本願寺京都市山科区西野山階町、左義長町別名 野村御坊、山科御坊 城?主 本願寺蓮如、実如、証如 築城?年代 文明十五年(1483) 保存状態 ★★★★☆ 訪ねやすさ ★★★★★ みどころ 大土塁と水堀跡 その他 遺構は住宅地に点在 |
| 山科中央公園に残る大土塁 | |
広大無辺の法城京都市内から山科へ行くには、粟田口から東山を越えなければならない。南禅寺わきから山科に越える蹴上の坂は、かつて路面を走っていた京阪京津線があえぎながらとろとろと登った ところ。自転車のペダルに力が要る。降りるのは爽快で、東海道線がみえるあたり、天智天皇の陵墓前まで来ると もう山科の中心街は近い。 私は、あんまり仏教のことを知らない。同じくあまり仏教にくわしくない人でも、一向宗の本願寺といえばイメージは浮かぶかもしれない。 加賀に「百姓ノ持タル国」を出現させ、信長はじめ各地の戦国大名にとって最大の脅威となった武装宗教といった印象が強い。日常的に戦乱が起こり、そうした不穏な世相を利して教線を延ばした本願寺である。武家の争いごとへの関与を避けたがっていた蓮如も、有事のことは常に考えていたのだろう。山科本願寺は、その蓮如がこの地に建立した、「城壁のある寺」というより「寺のかっこうをした城塞」である。 文明七年(1475)、自分の意思を超えて暴走をはじめた吉崎寺内町に別れを告げた蓮如は、いったん河内に身を引き、新たな宗教都市の構想を練り始めた。そんな蓮如に、土地の提供を申し出たのが海老名五郎左衛門という信者だった。海老名は山科七郷のうち、野村郷の指導者だったので、付近の百姓たちも海老名に習って門徒になる人が多かった。また、京都の入口にあたる山科の地は、これまで蓮如が布教してきた近江や北陸への連絡にも都合がよく、新たな拠点として申し分のない土地であった。蓮如はここに吉崎に代わる本拠を置くことを決意、文明十年(1478)に山科に転居し、伽藍堂塔の建設に着手した。 山科本願寺の造営は翌文明十一年(1479)から、徐々に進行していく。まず、自らの住居となる寝殿の建設がはじまり、その翌年は御影堂、さらに翌十三年(1481)には阿弥陀堂が次々と山科盆地の真ん中に姿を現した。寝殿以外の宗教施設は、みな門徒の寄付によって造られたという。寺の周りには末寺や各地から集まった門徒、郷民や商工業者たちが集住し、文明十五年(1583)「寺中広大、無辺荘厳、さながら仏国の如し」といわれる一大宗教都市が完成した(以上『寺内町の研究』第二巻など)。 蓮如は、寺内町の周囲に二重、三重の土塁、水堀をめぐらせ、「仏国」を外部の戦火から守ろうとした。近世城郭の総構えのはしりともいえるこの防塁は、完成から50年間、山科の町を守り続けた。だが、不落の法城にも、滅亡の時はきた。天文元年(1532)、細川晴元は洛中の法華一揆を煽動し、畿内で猛威を振るう一向宗を抑えようとした。八月二十四日、法華一揆は晴元や近江の六角定頼の後援のもと、山科の防塁を強行突破、ついに本願寺と寺内町は火の海に包まれた。戦後、晴元は「本願寺の城をわる」と称し、壁を崩し堀を埋めた(経厚法印日記、言継卿記)。よほど、山科の防塁にてこずったのだろう。当時の法主証如は、有名な石山本願寺に移り、その後二度と山科に戻ることはなかった。
|
|
探訪のしおり国道1号線を少しだけ入る。大土塁のある中央公園は山科郵便局の前。御本寺、西宗寺あたりは道が狭く入り組んでいるので、公園付近に駐車して歩いた方が無難でしょう。 最寄駅JR東海道線山科駅または地下鉄東西線東野駅。 |
|
| 洛中洛外の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |
 冒頭に、「寺のかっこうをした城塞」と書いた。それが誇張でないことは、 現在山科郵便局前にある山科中央公園に行けば、納得してもらえるだろう。 この公園は蓮如の家族が居住した本願寺「内寺内」の東北角にあたる。 運動場の北側を囲む小山が目に入るが、これは自然の丘ではない。 人工的につき固めて盛り上げた土塁である。 土の城壁としては類をみない規模で、上に登ると隣りのマンションの三階から四階と視線があう(覗かないように!)。高さ7メートルを測るといい、マンション側の土地が低いので、実際はそれ以上に高く感じる。これが山科寺内滅亡時の遺構としても、当時の京都周辺でこれだけの高さと幅をもった城壁は他にない。3、40年後の遺構と思われる 細川藤孝の勝龍寺城がやっと同規模の土塁を一部に採用している程度だ。 いかに本願寺の築城(?)技術が進んでいたかをうかがうに充分な遺跡といえる。土塁上はかなり広い馬踏となっており、北を走る東海道を監視する櫓があった。土塁の北側には「様子見町」という地名が残っている。この土塁の北すそは深い窪地となり、今小さなコートになっている。これは水堀の跡という。
冒頭に、「寺のかっこうをした城塞」と書いた。それが誇張でないことは、 現在山科郵便局前にある山科中央公園に行けば、納得してもらえるだろう。 この公園は蓮如の家族が居住した本願寺「内寺内」の東北角にあたる。 運動場の北側を囲む小山が目に入るが、これは自然の丘ではない。 人工的につき固めて盛り上げた土塁である。 土の城壁としては類をみない規模で、上に登ると隣りのマンションの三階から四階と視線があう(覗かないように!)。高さ7メートルを測るといい、マンション側の土地が低いので、実際はそれ以上に高く感じる。これが山科寺内滅亡時の遺構としても、当時の京都周辺でこれだけの高さと幅をもった城壁は他にない。3、40年後の遺構と思われる 細川藤孝の勝龍寺城がやっと同規模の土塁を一部に採用している程度だ。 いかに本願寺の築城(?)技術が進んでいたかをうかがうに充分な遺跡といえる。土塁上はかなり広い馬踏となっており、北を走る東海道を監視する櫓があった。土塁の北側には「様子見町」という地名が残っている。この土塁の北すそは深い窪地となり、今小さなコートになっている。これは水堀の跡という。 御影堂など本願寺の中心が置かれた「御本寺」にも、西側に断続して 「城壁」が残っている。こちらは「内寺内」の土塁ほど高くはないが、 よく整形された土塁が曲輪の西北隅から南北に、国道一号線を越えた先まで続く。途中に門跡とおぼしき部分も見受けられ、土塁に沿って一段低くなった堀跡がよく残っている。堀の外側には海老名五郎左衛門が開いた西宗寺があり、西出丸の役割を果たしていた。現在境内に「蓮如大往生の地」として銅像が建てられており、、山科中央公園の東には蓮如の墓も祀られている。
御影堂など本願寺の中心が置かれた「御本寺」にも、西側に断続して 「城壁」が残っている。こちらは「内寺内」の土塁ほど高くはないが、 よく整形された土塁が曲輪の西北隅から南北に、国道一号線を越えた先まで続く。途中に門跡とおぼしき部分も見受けられ、土塁に沿って一段低くなった堀跡がよく残っている。堀の外側には海老名五郎左衛門が開いた西宗寺があり、西出丸の役割を果たしていた。現在境内に「蓮如大往生の地」として銅像が建てられており、、山科中央公園の東には蓮如の墓も祀られている。 「御本寺」「内寺内」「寺内町」など城壁の内側は、現在住宅地となって 開発が進んでおり、当時の面影はない。近年土塁の一部も宅地化により破壊されたようだ。
寺内町としても、諸国に先駆ける「平城」としても、全国的に貴重な遺跡。 住民と行政、業者の理解で、残存部分だけでも後世に伝えてほしい。
「御本寺」「内寺内」「寺内町」など城壁の内側は、現在住宅地となって 開発が進んでおり、当時の面影はない。近年土塁の一部も宅地化により破壊されたようだ。
寺内町としても、諸国に先駆ける「平城」としても、全国的に貴重な遺跡。 住民と行政、業者の理解で、残存部分だけでも後世に伝えてほしい。