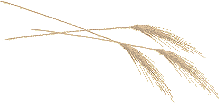 |
洛中洛外の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |
 山腹に残る横堀(塹壕)の土塁 山腹に残る横堀(塹壕)の土塁 |
船岡山城京都市北区紫野北舟岡町別名 船崗山城、山名城など 城主 大内、山名、細川氏など 築城年代 応仁元年(1467) 保存状態 堀がきれいに残る 訪ねやすさ かんたんに行けます みどころ 中腹の横堀、建勲神社 その他 夜は危ないらしい(噂) |
乱世に翻弄された小山かつての朱雀大路といわれる千本通は、今出川の交差点を過ぎると坂が次第にきつくなっていく。西陣の町屋に埋め尽くされたこの傾斜地の中に、ぽっかりとなだらかな丘の緑がみえる。この低い丘が、戦国の争乱に多くの血を吸った城跡とは、にわかに信じられない。丘陵上には明治になって織田信長を祀る建勲神社が建立され、尾根も公園化して城の雰囲気は薄れている。だが、一歩踏み込むと、北側山腹を縫うように横堀が走っているのがはっきり確認でき、ここに城があったことを伝えてくれる。 船岡山は平安京建設のさい、都を守る四神のうち北方の守護・玄武に見立てられ、都市計画の基軸とされたことで知られる。都の平安を守るこの丘も、戦国争乱の波から逃れることはできなかった。 応仁元年(1467)、西軍山名宗全に味方した西国最強の守護・大内政弘は、大軍を催して山口を発向、摂津を守備する東軍赤松政則の兵を撃破して、入京を果たした。その政弘が陣を張ったのが、この船岡山であった(宗賢卿記)。船岡山は、京都市内から丹波へと越える長坂口を押える好位置にあり、大内勢は細川勝元が丹波の味方と連絡するのを阻止する目的で、陣を構えたものだろう。『碧山日録』応仁二年九月七日条に、「西兵自去歳、以船崗山為城」とあるので、政弘の着陣と共に船岡山が城塞化したことがわかる。
このように、たびたびの東軍の襲撃にもかかわらず、船岡山城は落ちる気配をみせない。同じ年の九月、丹波から嵯峨野方面に侵攻した丹波守護代内藤氏に呼応するため、勝元は本格的に船岡奪取に動いた。攻撃軍の大将は、山名一族ながら東軍に投じた山名是豊、何度か船岡攻めの経験のある薬師寺与一、赤松政則の宿老浦上則宗、奈良興福寺の成身院光宣ら。東軍は山の三方から遮二無二船岡山を攻撃したが、この方面は文武に秀でた小鴨安芸守之基(山名教之の重臣)が堅固に守っており、歯が立たない。そこで、浦上則宗は足軽の一若に命じ、五、六十名の少人数で正伝寺わきより遊撃軍を迂回させ、守備の薄い一色の陣を攻撃させた。一色義直は油断して多くの兵を嵯峨野方面に繰り出しており、浦上勢はこれを破って堀を乗り越え、石築地をよじ登って陣屋に火をかけた。たまたま、大将の山名教之は病気療養中で船岡山におらず、小鴨之基と山名三郎(常陸介の子とも、教之の子ともいう)は獅子奮迅の働きの末、戦死。ついに船岡山は焼き滅ぼされた。この戦闘で千本辺りも焦土と化したという(山科家礼記、碧山日録、応仁別記)。 勝元らは船岡山城を味方陣地として確保しておこうと言ったが、成身院光宣が「利を得て利を失うことになる。この城を保つには紫野と今宮に伝いの城がなければ無理だ、さっさと捨てましょう」と進言。船岡山は捨てられ、再び西軍一色義直の確保するところとなった。以後、乱の終息するまで、一色勢がこの地に駐屯していたらしい(応仁別記、大乗院寺社雑事記)。
永正八年(1511)になって、播磨守護赤松義村の与力に勇気づけられた義澄・澄元派は、大規模な軍事行動を開始。澄元は阿波から堺に上陸し、近江の甲賀衆・河内守護畠山義英の援軍を加えて京都に進撃、赤松勢は摂津に攻め込んで高国方の鷹尾城を攻略、伊丹城に迫った。八月、澄元方の大挙来襲に驚いた義稙・高国・義興はいったん丹波に退却し、態勢をととのえる。二十三日、細川・大内の連合軍は京都を一望のもとにおさめる長坂山(堂ノ庭城)に布陣した。眼下の船岡山には、すでに澄元方の細川右馬頭政賢が息を凝らして待ち構えていた。翌日、長坂から連合軍は怒涛のごとく攻めくだり、有名な船岡山合戦の火ぶたが切って落とされた。 |
|
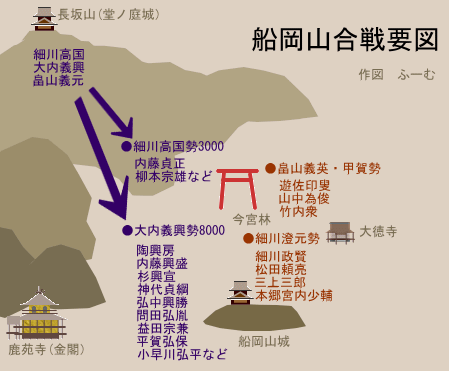 |
|
|
澄元は、船岡山に政賢をはじめ幕府官僚の松田頼亮、奉公衆の三上三郎・本郷宮内少輔をおき、今宮神社の森にも遊佐河内入道印叟の率いる畠山勢、山中・竹内ら甲賀勢を配置して長坂から洛中への侵攻を阻止させた。連合軍のほうは、高国の部将内藤貞正・柳本宗雄らが今宮へ、大内勢が船岡山へそれぞれ攻撃をしかける。戦闘は激烈を極めたが、なかでも陶興房らに統率された大内勢の戦いぶりは凄まじく、船岡山を一挙に屠ろうと猛攻を加えた。守る澄元勢もここを先途と奮戦し、大内方の老将問田弘胤を討ち取るなど頑強に抵抗したが、ついに雪崩を打って総退却。実に3800余の戦死者を野にさらして敗走したのであった。松田頼亮は文筆官僚の身にかかわらず、最後まで船岡にとどまって戦死、澄元本陣へとひたすら逃れようとした指揮官の細川政賢は、敵の追い討ちをかわし切れず、羅漢橋(現在の今出川通と小川通が交差する地点)で自刃した。遊佐印叟も今宮の戦いで高国に捕縛され、翌日刑場の露と消えた。この一戦で細川澄元は再起不能と思われるほどの大打撃をこうむったのである(実隆公記・後法成寺尚通公記・厳助往年記・拾芥記・萩藩閥閲録・益田文書・平賀文書・小早川文書・瓦林政頼記など)。 その後も船岡山は陣城として使用され、足利義輝・細川晴元らが天文二十二年(1553)八月にここにいたことが『言継卿記』にみえる。これは、三好長慶との戦闘のさい仮陣を構築したもので、ほどなく義輝らは丹波方面に逃れている。
★追記:このページで使用している写真は、はんかつうさまのカメラを借りて撮影したものです。この場を借りて御礼申し上げます。 探訪のしおり千本北大路の交差点南詰を東に下りていきます。本屋さん、郵便局…と通過し、二つ目の信号まで進みます。そこのパチンコ屋さんとガソリンスタンドの間の道を右折します。正面にみえる森が船岡山です。登り口はここ以外にも、東側の建勲神社参道、千本北大路交差点から一つ目の信号の脇など、あちこちあります。詳しくは案内まっぷをご覧下さい。街中の小高い丘なので、京都市中の展望は最高。八月の五山送り火の夜にはビュースポットとして、観光客でごった返します。 最寄駅京都市営地下鉄烏丸線の北大路駅。駅にバスターミナルがあり、そこからバスで船岡山バス停(建勲神社前でも可)まで行けば、すぐです。 |
|
| 洛中洛外の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |
 その後、船岡山城は宗全の一族で備前守護の山名教之、丹後守護の一色義直が守備した。日記類に散見される「宗全之城」「山名城」とは、この船岡山城のことらしい。応仁二年(1468)四月一日、山名の陣所で「西楼」(井楼)の建設がはじまった。井楼とは井桁状に骨組みを組み合わせた高層の櫓のこと。細川勝元は重臣の薬師寺与一元一を馳せ向かわせ、矢倉(櫓)の上から石つぶてをぶつけて工事を妨害させた。このため、この日の工事は進捗せず、二重目までしか組み上がらなかったが、十四日には「宗全の城」に高さ七丈余という巨大な井楼が完成した。七月八日朝には、「山名城」で堀の掘削作業が行われた。今、山の中腹を囲饒する横堀は、このときのものだろうか。またまた勝元は薬師寺与一を攻め込ませ、一時城郭を奪取したものの、山名方でもかねて襲撃に備え、大野伏を潜ませていた。細川勢は隠れていた敵兵に意表を衝かれ、手負百十余人を出して敗走した(山科家礼記)。
その後、船岡山城は宗全の一族で備前守護の山名教之、丹後守護の一色義直が守備した。日記類に散見される「宗全之城」「山名城」とは、この船岡山城のことらしい。応仁二年(1468)四月一日、山名の陣所で「西楼」(井楼)の建設がはじまった。井楼とは井桁状に骨組みを組み合わせた高層の櫓のこと。細川勝元は重臣の薬師寺与一元一を馳せ向かわせ、矢倉(櫓)の上から石つぶてをぶつけて工事を妨害させた。このため、この日の工事は進捗せず、二重目までしか組み上がらなかったが、十四日には「宗全の城」に高さ七丈余という巨大な井楼が完成した。七月八日朝には、「山名城」で堀の掘削作業が行われた。今、山の中腹を囲饒する横堀は、このときのものだろうか。またまた勝元は薬師寺与一を攻め込ませ、一時城郭を奪取したものの、山名方でもかねて襲撃に備え、大野伏を潜ませていた。細川勢は隠れていた敵兵に意表を衝かれ、手負百十余人を出して敗走した(山科家礼記)。 次いで、船岡山がクローズアップされるのは、約五十年後の永正八年(1511)。実力者細川政元の暗殺後、畿内の情勢は混迷を深め、細川氏も政元の養子澄元と高国が相争っていた。この混乱を衝いて、西国からまたまた大内義興が前将軍足利義稙を擁して挙兵、細川高国とよしみを通じて上洛を果たす。ときの将軍足利義澄は、細川澄元と共に近江に脱出し、高国と義興は義稙を新将軍とした。義澄・澄元派はたびたび政権奪取をはかったが、大内勢の軍事力の前になすすべもなく、三年間はふるわなかった。
次いで、船岡山がクローズアップされるのは、約五十年後の永正八年(1511)。実力者細川政元の暗殺後、畿内の情勢は混迷を深め、細川氏も政元の養子澄元と高国が相争っていた。この混乱を衝いて、西国からまたまた大内義興が前将軍足利義稙を擁して挙兵、細川高国とよしみを通じて上洛を果たす。ときの将軍足利義澄は、細川澄元と共に近江に脱出し、高国と義興は義稙を新将軍とした。義澄・澄元派はたびたび政権奪取をはかったが、大内勢の軍事力の前になすすべもなく、三年間はふるわなかった。 さて、以上の経歴から知られるように、船岡山城は臨戦用の陣城であって、恒久的な城郭施設が存在したかどうかはわからない。必要に応じて井楼が組まれ、逆茂木が植えられ、敵に備えていたのではなかろうか。曲輪や切岸もそれほど整形されたものはなく、兵士を配置するための平地がたくさん造成されている。ただ、冒頭にふれた堀は相当立派なものが造られている。北側中腹の横堀は、総延長三百メートルの大規模なもの。堀の外側は土塁になっており、さながら塹壕陣地の雰囲気をただよわせる。この堀は北尾根の曲輪群の方まで伸びており、移動用の通路としても使えそうだ。船岡の西尾根側、この横堀と頂上の曲輪の間の斜面には長細いテラスがあり、ここに兵士を置いて直下の塹壕に落ちた敵兵に矢の雨を降らせたものと考えられる。なお、建勲神社本殿裏に三重の堀切をともなう遺構が完存していると山下正男氏『京都市内およびその近辺の中世城郭』にあるが、現在この地は神社の神域として結界が張られており、見学できそうにない。
さて、以上の経歴から知られるように、船岡山城は臨戦用の陣城であって、恒久的な城郭施設が存在したかどうかはわからない。必要に応じて井楼が組まれ、逆茂木が植えられ、敵に備えていたのではなかろうか。曲輪や切岸もそれほど整形されたものはなく、兵士を配置するための平地がたくさん造成されている。ただ、冒頭にふれた堀は相当立派なものが造られている。北側中腹の横堀は、総延長三百メートルの大規模なもの。堀の外側は土塁になっており、さながら塹壕陣地の雰囲気をただよわせる。この堀は北尾根の曲輪群の方まで伸びており、移動用の通路としても使えそうだ。船岡の西尾根側、この横堀と頂上の曲輪の間の斜面には長細いテラスがあり、ここに兵士を置いて直下の塹壕に落ちた敵兵に矢の雨を降らせたものと考えられる。なお、建勲神社本殿裏に三重の堀切をともなう遺構が完存していると山下正男氏『京都市内およびその近辺の中世城郭』にあるが、現在この地は神社の神域として結界が張られており、見学できそうにない。