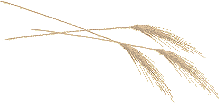 |
備前の城へ お城ひろいへ 落穂ひろいトップページへ |
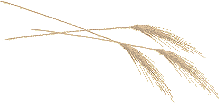 |
備前の城へ お城ひろいへ 落穂ひろいトップページへ |
 |
北曽根城岡山県和気郡和気町曽根別名 曽根城、名黒山城 城主 (伝)恒次隼人、明石景行、明石右近 築城年代 不明 保存状態 下草が刈られ、見学しやすい 訪ねやすさ けっこう急坂、岩場に注意 みどころ 本丸の石垣、巨岩を用いた門 その他 9/1〜11/30の期間は入山禁止 |
| 和気富士と呼ばれる秀麗な城山 | |
巨岩を利用した堅城JR山陽線の上り列車が吉井川を渡り終え、和気駅にすべり込むころ、左手に富士山に似た美しいかたちの山がみえる。通称「和気富士」と呼ばれるこの急峻な山頂に、岩石の塊のような城郭の跡が残されている。 美作方面から滔々として流れ来る吉井川と金剛川の合流点に位置する本和気は、高瀬舟の停泊する川湊として栄え、江戸期には商家が軒を連ねていた。この本和気の町を見下ろす北曽根城は、河川交通を扼する要衝として、重要な役割を果たしていたと思われる。
恒次氏を押えて和気地方を制した宗景は、北曽根城に宿老明石行雄(景親)の一族景行を入れたらしい。景行は行雄の長男とも弟ともいわれる人物だが、主君宗景から一字を拝領しているところをみると、行雄同様重用されていたようだ。天神山城を居城とする宗景にとっては、北曽根は本拠地南方を直接押える重要拠点であり、特に重臣の子弟を入城させたものと思われる。永禄十一年(1568)九月、景行は城の東にある由加神社に征矢を寄進している。この月、主君宗景は播磨出兵に着手しており、戦勝を祈願して奉納したのかもしれない。
景行のあと、北曽根城には一族の明石右近が入った。右近は景行の実子とも弟とも言われるが、『吉備前鑑』は右近の代に山上の城を廃し、麓に館を設けて住むようになったとしている。あるいは、宇喜多氏による城割りが存在したのかもしれない。右近は朝鮮出兵に参加して戦傷死したといわれ、『備陽記』は右近の死後城が破却されたと伝えている。いずれにせよ、伝承からは関ケ原以前に廃城とされたらしいようすがうかがえる。 |
|
 |
|
| 北櫓からの眺望。吉井川上流右にナイフの切っ先のような天神山城がくっきりみえる。 | |
|
城郭の部分からの眺望は抜群で、本丸北西の「北櫓」から天神山城を望むことができる(天神山からもこの城がみえます)。東は明石一族の本城といわれる吉永の東山城との連絡もきき、両城連携すれば船坂峠を越えて播磨から侵入する敵軍に速やかに対応できそうだ。南に下がった尾根上の岩肌に立てば、西に大きくうねる吉井川の流れや、和気、吉永方面の眺めが素晴らしい。夕暮れ時や川霧が出たときなど、なかなか捨て難いものがある。 探訪のしおり和気付近の地図は、案内まっぷをご覧下さい。自動車の方は、ちょっと離れていますが和気町役場入口にある水辺の広場駐車場に駐車するといいでしょう。金剛川に歩行者用の橋がかかっているので渡ります。この橋の目の前にそそり立つ山が城址です。橋を渡り、横断歩道を渡った先に続く道を奥に進んで下さい。しばらく進むと、右手に赤い鳥居のある山道があります。ここが登山口です。ひたすら登りましょう(^^)速い人は15分くらいで登れるでしょう。ちょうど息切れするあたり(?)に岩場があり、見晴らしは最高ですがくれぐれもお気をつけ下さいm(__)m 最寄駅JR山陽本線和気駅。城山は駅の目の前で、富士山のかたちをしているのですぐわかります。駅前の道をまっすぐ北に進むと、「探訪のしおり」に書いた歩行者用の橋があります。渡った後は同じです。和気の町は狭いところが多いので、本当は電車で行くほうが訪ねやすいです。 |
|
| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |