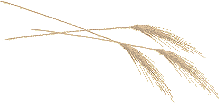 |
備前の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |
 |
乙子城岡山県岡山市乙子別名 音湖城 城主 伝・宇喜多直家 築城年代 不明 保存状態 一部墓地となるが、まあまあ 訪ねやすさ 看板、登山道が整備 みどころ 土壇、礎石、列石遺構 その他 吉井川河口、海がみえます |
| 左の小山が乙子城。遠くに瀬戸内の島がみえる | |
直家最初の居城西大寺の沖のほう、という。厳冬の二月、有名な裸祭りの行われる観音院のある西大寺より南を「沖」と呼んでしまう。かつて、西大寺は吉井川河口の港町としても栄えていた。江戸時代に入って干拓が進む以前、たしかに西大寺の南方は海があり、「沖」と呼んでも差し支えなかった。いまでも、観音院のそばまでくると「海」を意識させる何ものかが残っている。乙子城はまさに、この西大寺の沖にある。吉井川河口の突端にあり、戦国時代には城郭の麓まで海が広がっていた。要地といえばかなりの要地で、児島、犬島など瀬戸内の島々を望み、吉井川を上り下りする船を抑える格好の場所だ。その雰囲気は上に載せた写真からも少しはうかがえると思う。
それはともかく、城主となった直家のもとには、旧家臣たちが押しかけた。持ち分以上の人員を召し抱えた直家は、知行だけで生活していくことができなくなり、倹約のため「失食」として月に三〜五度食を絶って兵糧にあてた。家老の岡、長船らも近所で泥棒して何とかやりくりしていたという(戸川記など)。何ともみじめなお話だが、この苦しい乙子城時代を経ることで、宇喜多直家主従は戦乱を生き抜くたくましさを身に付けていった…ということになっている。直家はその後、浦上政宗に味方していた同族宇喜多大和守を討ち、その功労を宗景に認められて上道郡奈良部城を与えられ、こちらに移った。だいたいこれが弘治二年〜三年(1556〜57)ごろのことだということが研究により判明しつつある(森俊弘氏「岡山藩士馬場家の宇喜多氏関連伝承について」)。その後、直家は乙子城を弟の忠家に預けたと『備前軍記』にあるが、根拠はよくわからない。『吉備前鑑』には宇喜多基家(元家、忠家の息子)が居城したとも書いている。 |
|
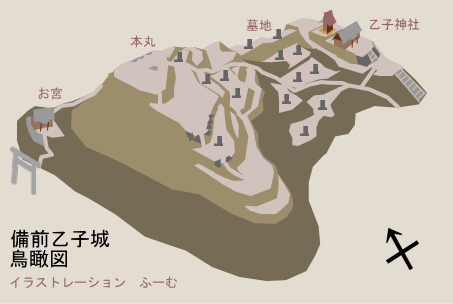 |
|
|
その後、乙子城の動静は全くわかっていない。ただ、直家に滅ぼされた浦上宗景の残党が、天正三年(1575)以降乙子城南方の幸島を拠点に暗躍しており(坪井文書など)、児島海峡を挟んだ向こう岸の小串に毛利方の高畠和泉守が在城していた(萩藩閥閲録など)ことなどを考えると、これらへの備えとして天正十年(1582)ごろまで機能していた可能性が高い。
探訪のしおり城跡までの道は、案内まっぷをご覧下さい。吉井川堤防沿いの道は狭いので、対向車には十分ご注意を。登山道は三ヶ所ほどあります。山の北側、「宇喜多直家国盗りはじめの地」の石碑が立つ空き地の向こう、石鳥居をくぐって山道を入ると、本丸に直接上がれます。ここが一番整備されていて、近道です。南側にも、乙子神社参道から入る道と、東側の案内板から神社境内に入る道とがあり、どちらからでも簡単に登れます。まあ、低い丘ですのでお好きなルートからどうぞ。なお、東の登り口、看板裏の崖上に五輪塔があって児島高徳の父、和田範長の墓といわれています。ほんまかなあ^^; 最寄駅JR赤穂線西大寺駅。城址は駅から遠く、バスも通っていないので、クルマかバイクか自転車で向うのがいいでしょう。 |
|
| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |
 乙子城は、のちに戦国大名にのし上がる宇喜多直家の最初の居城として知られている。天文十三年(1544)、守護赤松晴政との合戦で初陣し、手柄を立てた直家は、主君浦上宗景からはじめてこの城を預かり、所領三百貫を与えられた。乙子城は浦上宗景が児島近海の備えとして吉井川河口に築いたものの、危険な場所なので誰も城番を買って出る者がいなかった。そこで立候補した直家にこの城を任せることになったというのが、『備前軍記』で著名な直家立身説話だ。この話の核心部分は、備前で最も古い地誌『備前記』にも載っており、古くからの伝承らしい。ただ、『備前軍記』のいう天文十三年とか、初陣の手柄話とかは古い説話には一言も触れられていない。また、『吉備前秘録』によれば宇喜多能家のころから、『戸川記』によれば直家の父興家のころから乙子に在住していたともいわれる。事実はどうだったのか、今のところ知る手立てがない。
乙子城は、のちに戦国大名にのし上がる宇喜多直家の最初の居城として知られている。天文十三年(1544)、守護赤松晴政との合戦で初陣し、手柄を立てた直家は、主君浦上宗景からはじめてこの城を預かり、所領三百貫を与えられた。乙子城は浦上宗景が児島近海の備えとして吉井川河口に築いたものの、危険な場所なので誰も城番を買って出る者がいなかった。そこで立候補した直家にこの城を任せることになったというのが、『備前軍記』で著名な直家立身説話だ。この話の核心部分は、備前で最も古い地誌『備前記』にも載っており、古くからの伝承らしい。ただ、『備前軍記』のいう天文十三年とか、初陣の手柄話とかは古い説話には一言も触れられていない。また、『吉備前秘録』によれば宇喜多能家のころから、『戸川記』によれば直家の父興家のころから乙子に在住していたともいわれる。事実はどうだったのか、今のところ知る手立てがない。 現在城跡の大半は墓地、畑、神社の境内となっており、変形している部分もあるかもしれない。主郭部は川沿いの山頂部を中心に東南に向って四段の曲輪を階段状に配置している。二段目の曲輪が最も広く、頂部の曲輪はその北側を櫓台状に固めている。山頂部の曲輪には平べったい礎石一つと、曲輪北側の肩部を押える列石が残っている。この列石は、南に下る他の曲輪の肩部にも使用されている。『日本城郭大系』には、本丸北側に土塁が遺存すると書いてあるが、それらしきものは見当たらない。曲輪の東側は、乙子神社との谷間に向ってほとんど墓地となっている。細い尾根を越えたところに乙子神社があり、ここにも主郭部から独立した主要な曲輪(二の丸?)があったという。江戸時代の古図には神社を中心に曲輪数段が描かれている。こちらの塁壁裾部も列石で補強されている。
現在城跡の大半は墓地、畑、神社の境内となっており、変形している部分もあるかもしれない。主郭部は川沿いの山頂部を中心に東南に向って四段の曲輪を階段状に配置している。二段目の曲輪が最も広く、頂部の曲輪はその北側を櫓台状に固めている。山頂部の曲輪には平べったい礎石一つと、曲輪北側の肩部を押える列石が残っている。この列石は、南に下る他の曲輪の肩部にも使用されている。『日本城郭大系』には、本丸北側に土塁が遺存すると書いてあるが、それらしきものは見当たらない。曲輪の東側は、乙子神社との谷間に向ってほとんど墓地となっている。細い尾根を越えたところに乙子神社があり、ここにも主郭部から独立した主要な曲輪(二の丸?)があったという。江戸時代の古図には神社を中心に曲輪数段が描かれている。こちらの塁壁裾部も列石で補強されている。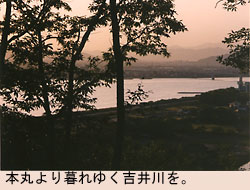 全体的にみて、主郭部や神社付近の曲輪肩部を丸っこい石による列石で固め、本丸に礎石を使用しているが、本格的な石垣はなく瓦の散布もみられない。宇喜多氏は天正前期から十年(1582)前後にかけて順次主要な支城を瓦葺に改修していったらしい(乗岡実氏「中世山城の瓦三題」)。これらの城には本格的な石垣が構築されている。乙子城にはそれがないこと、さらに上に述べた周辺事情から考えると、秀家期に入って間もなく重点整備の対象から外れ、廃れていったのであろう。
全体的にみて、主郭部や神社付近の曲輪肩部を丸っこい石による列石で固め、本丸に礎石を使用しているが、本格的な石垣はなく瓦の散布もみられない。宇喜多氏は天正前期から十年(1582)前後にかけて順次主要な支城を瓦葺に改修していったらしい(乗岡実氏「中世山城の瓦三題」)。これらの城には本格的な石垣が構築されている。乙子城にはそれがないこと、さらに上に述べた周辺事情から考えると、秀家期に入って間もなく重点整備の対象から外れ、廃れていったのであろう。