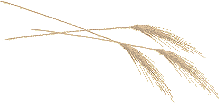 |
備前の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |
 |
うな山城岡山県岡山市御津伊田別名 高山城 城主 伝・長崎行春・行兼父子 築城年代 不明 保存状態 なかなか良好 訪ねやすさ マイナー城にしては楽 みどころ 堀切・土塁・城主の墓 その他 古墳を城郭に転用している |
| 堀切(手前)越しに主郭を望む | |
コンパクトな峠の要害赤坂町から御津町へ越える峠を「伊田越」とか「山口乢」といい、カーブが多くて今でも中々の難所である。この峠より西側が、いわゆる金川城主松田氏の本領であり、この峠一帯は浦上・松田両氏の勢力の境目の様相を呈していた。うな山城は、この峠に最も近い場所に築かれた、小さな要害である。
その後、半世紀ほどを経て長崎与七郎行兼という人物が登場してくる。行兼は『備陽国誌』のいう四郎左衛門(行春)の次男という(墓碑銘)。天文末年(1554年ごろ)、行兼は尼子晴久の命を受け、難波職経・松田氏ら近隣諸豪と共に倉淵城(所在地不明)に在番している(黄薇古簡集)。天文二十二年(1553)、尼子勢の備前侵攻によって浦上政宗に従っていた「国中の輩」が離反しており(同前)、長崎行兼らもこの時政宗を見限って尼子晴久に味方したものかもしれない。 その後、長崎氏の動向はつかめないが、行兼の墓碑銘によると、宇喜多直家に城を攻め落とされ帰農したのだという。行兼は長命で、七十三歳まで生き永らえ慶長年間に病没した(墓碑銘)。 |
|
  |
|
|
なお、主郭の土塁手前には、子孫が寛延二年(1749)に建立した「妙法道智居士」こと長崎行兼の墓が残っている。 ※うな山城の探訪・絵図作成にあたっては、『御津の山城』(御津町ワンダークラブ歴史班編/2002年)が大いに参考になりました。この本がなければ、うな山城の位置を探し当てることが出来たかどうか…記して感謝申し上げますm(_ _)m。 探訪のしおり城跡までの道は、案内まっぷをご覧下さい。上伊田集落の山側の道路を北に進むと、古い石の道標(左:新庄・平岡 右:平木・由津里)が立つ三叉路があります。この地点の右手、防火用水の横の道を東の山に向って歩いていくと、山沿いの墓地の入口がみえます。この墓地の上が城址です。申しわけないことですが、墓地内を遠慮がちに通り抜け、尾根を目指すことになります。山は低く、山道も残っているので比較的楽に城跡までたどり着けるでしょう。 最寄駅付近に駅はありません(^_^; |
|
| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |
 うな山城がいつ築かれたのかは、史料不足でほとんどわかっていない。江戸時代の地誌『備陽国誌』はただ一点、城主が長崎四郎左衛門なる者であったと伝えている。長崎氏について出自などは不明だが、備前守護代浦上氏に仕えていたことが文書より知られる。明応年間、守護代の浦上宗助は長崎太左衛門入道を呼び出し糾明した結果、その孫・長崎平左衛門に相伝の知行を安堵している(黄薇古簡集)。長崎氏の知行地は具体的にわからないが、うな山城のある上伊田周辺にその本領があったのであろうか。
うな山城がいつ築かれたのかは、史料不足でほとんどわかっていない。江戸時代の地誌『備陽国誌』はただ一点、城主が長崎四郎左衛門なる者であったと伝えている。長崎氏について出自などは不明だが、備前守護代浦上氏に仕えていたことが文書より知られる。明応年間、守護代の浦上宗助は長崎太左衛門入道を呼び出し糾明した結果、その孫・長崎平左衛門に相伝の知行を安堵している(黄薇古簡集)。長崎氏の知行地は具体的にわからないが、うな山城のある上伊田周辺にその本領があったのであろうか。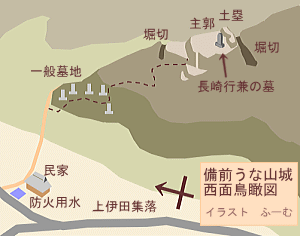 城址は上伊田集落の東方尾根上に残されている。伊田越・平木峠を扼する要害だが、峠そのものに面してはおらず、山に遮られて東方への見通しは全く効かない。むしろ、西方から二つの峠へ向う街道を監視する位置に築かれている。本来浦上氏被官であった長崎氏の城ということで、東方よりも西方の松田領からの侵入者を監視できる場所が選ばれたのだろう。早くに『改修赤磐郡誌』も地勢について検討した結果、浦上方の築いた要害と推定している。その縄張は図示したとおり、そこそこ広い主郭の前面両角に腰曲輪を設けただけの、実にコンパクトなもの。山城としてはやはり最小の部類に入るだろう。
城址は上伊田集落の東方尾根上に残されている。伊田越・平木峠を扼する要害だが、峠そのものに面してはおらず、山に遮られて東方への見通しは全く効かない。むしろ、西方から二つの峠へ向う街道を監視する位置に築かれている。本来浦上氏被官であった長崎氏の城ということで、東方よりも西方の松田領からの侵入者を監視できる場所が選ばれたのだろう。早くに『改修赤磐郡誌』も地勢について検討した結果、浦上方の築いた要害と推定している。その縄張は図示したとおり、そこそこ広い主郭の前面両角に腰曲輪を設けただけの、実にコンパクトなもの。山城としてはやはり最小の部類に入るだろう。 ただし、小さいながらもうな山城は防御にいろいろと気をつかっており、主郭の背後、主峰尾根側は土塁を盛り上げ、その外側を立派な堀切でバッサリ切断している。堀切の両端は長い竪堀となっており、この遺構は夏場でも明瞭にみることが出来た。また、ここの土塁は古墳の盛り土を利用して造成した珍しいもので、現在土塁の造成土の一部が掘り返され、横穴式の石室がぱっくり口を開けている。城の正面には大規模な防御設備はないけれど、主郭の切岸は高く、腰曲輪の先端にも小規模ながら堀切が施され、一応の体裁は整えている。戦略上重要な地点に築かれているだけに、小さいながらも見どころの多い山城といえよう。
ただし、小さいながらもうな山城は防御にいろいろと気をつかっており、主郭の背後、主峰尾根側は土塁を盛り上げ、その外側を立派な堀切でバッサリ切断している。堀切の両端は長い竪堀となっており、この遺構は夏場でも明瞭にみることが出来た。また、ここの土塁は古墳の盛り土を利用して造成した珍しいもので、現在土塁の造成土の一部が掘り返され、横穴式の石室がぱっくり口を開けている。城の正面には大規模な防御設備はないけれど、主郭の切岸は高く、腰曲輪の先端にも小規模ながら堀切が施され、一応の体裁は整えている。戦略上重要な地点に築かれているだけに、小さいながらも見どころの多い山城といえよう。