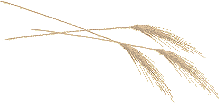 |
備前の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |
 |
西谷城岡山県岡山市御津新庄別名 新庄城 城主 伝・松田彦次郎歴代 築城年代 不明 保存状態 比較的良好 訪ねやすさ 山が低いのでかんたん みどころ 曲輪、松田氏供養塔 その他 居館的な丘城 |
| 北尾根の曲輪群。奥に見えるのが本丸 | |
新庄松田氏の居城金川城にあって西備前に覇をとなえた松田氏には、多くの支族があった。金川の町から北東の谷あいに、新庄という小さな盆地がある。この新庄の谷の奥に、松田一族の居城・西谷城があった。 この付近は、中世の平岡郷にあたる。その郷内で新しく開発された場所が平岡新庄と呼ばれた。この平岡新庄にいつ頃松田氏が入部したか、史料不足でわからないが、『庶軒日録』に「松田新庄殿」がみえており、ここに松田氏の支族が居住していたことは間違いない。
上野介家はほぼ日常を京都で送り、将軍の近習として活動していたが、新庄松田氏はもっぱら国許にあって備前の御家人たちの中心となって働いた。文明六年(1474)十二月、松田彦次郎(元貞)は幕府から小早川元平の備後高山城救援を命じられている(小早川家文書)。この彦次郎元貞は系図では金川城主松田元成の弟と伝えている。あくまで系図を重視するならば、元成が実弟を新庄松田氏に送り込み、跡を継がせたということかもしれない。その後、松田元成は守護赤松氏に挑戦し有名な福岡合戦が起こる。このとき、彦次郎も元成に合流して戦い、備前磐梨郡弥上村(岡山県熊山町)で戦死したというが、当時の史料では確認できない。 その後も西谷城の新庄松田氏は存続し、永禄年間の松田彦次郎は浦上宗景に従属して美作南部を転戦し、感状を与えられている(備前松田家文書)。そのため、永禄十二年(1568)の松田本家滅亡後も、彦次郎は浦上従属下の国衆として生き残った。天正二年(1574)、宇喜多直家が叛旗をひるがえした後も新庄松田氏は宗景側に味方し、翌年五月には天神山籠城に参加して宗景より褒賞された(同前)。宗景滅亡後、新庄松田氏は多くの所領を失ったようだが、宇喜多政権下でも新庄地区の土豪として余喘を保ち、江戸期にはそのまま帰農して現在に至るまで子孫が続いている。
全体として、大作りの本丸を中心に小郭を展開しただけの城で、土塁などの防御施設もなく、居館的レベルを脱していない。ただ、本丸正面の防御ラインを三段構えにするなど、正面の防衛に意を用いているようすはうかがえる。 探訪のしおり城跡までの道は、案内まっぷをご覧下さい。一本道なので、意外と迷うことはないと思います。金川から吉井町方面へ抜ける道路を、新庄の交番のところで北へ曲がり、五城村青空市場を通過してどんどん谷の奥へ進んでいくと、左手に消防団の倉庫と西谷公民館があります。この西側の丘陵上が城址です。 最寄駅付近に駅はありません(^_^;車かバイクがないと、難しい場所です…。 |
|
| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |
 子孫の残した文書、江戸期の伝承などから判断する限り、新庄松田氏は代々「彦次郎」を通称としたらしい。室町幕府奉公衆として出仕した松田上野介家の一族に、松田上野彦次郎満重なる者がおり、明徳三年(1392)の相国寺法要の際、将軍足利義満を護衛している(相国寺供養記)。この人物あたりから新庄松田氏は枝分かれした可能性がある。上野介家は山口殿とも呼ばれ、備前鳥取庄のうち山口(岡山県赤坂町山口とその一帯)をその基盤としていたと思われる。山口に近接する平岡新庄に上野介家の一族が入部した結果、新庄松田氏が成立したものであろう。
子孫の残した文書、江戸期の伝承などから判断する限り、新庄松田氏は代々「彦次郎」を通称としたらしい。室町幕府奉公衆として出仕した松田上野介家の一族に、松田上野彦次郎満重なる者がおり、明徳三年(1392)の相国寺法要の際、将軍足利義満を護衛している(相国寺供養記)。この人物あたりから新庄松田氏は枝分かれした可能性がある。上野介家は山口殿とも呼ばれ、備前鳥取庄のうち山口(岡山県赤坂町山口とその一帯)をその基盤としていたと思われる。山口に近接する平岡新庄に上野介家の一族が入部した結果、新庄松田氏が成立したものであろう。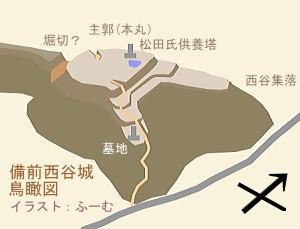 さて、城址は現在の西谷集落の西の丘上に残されている。室町幕府に仕えた国人の居城だが、規模・縄張からいって城というより居館といった風情である。本丸は集落西方の山地から舌状に突き出した丘の頂上にある。ここは方形のかなり広い郭で、居館を建てるにはじゅうぶんなスペース。西の尾根側と東の平地側が虎口状に切り込まれ山道が通っている。本丸背後には尾根を切断する堀切状のものがあるが、当時のものかどうか一考を要する(削れた地肌が妙に新しく感じる…)。本丸内には土塁などもなく、江戸後期に建立された松田元成・元貞の供養塔が侘しげにみえる。
さて、城址は現在の西谷集落の西の丘上に残されている。室町幕府に仕えた国人の居城だが、規模・縄張からいって城というより居館といった風情である。本丸は集落西方の山地から舌状に突き出した丘の頂上にある。ここは方形のかなり広い郭で、居館を建てるにはじゅうぶんなスペース。西の尾根側と東の平地側が虎口状に切り込まれ山道が通っている。本丸背後には尾根を切断する堀切状のものがあるが、当時のものかどうか一考を要する(削れた地肌が妙に新しく感じる…)。本丸内には土塁などもなく、江戸後期に建立された松田元成・元貞の供養塔が侘しげにみえる。 本丸両側面は切り立った急斜面なので、そのまま要害地形を利用している。曲輪群は傾斜の緩やかな正面を集中的にガードするかたちで築かれている。本丸正面にあたる東側は一段の犬走がテラス状に伸び、その下にはさらに帯曲輪がおかれ、ひな壇状の三段構えになって深い谷に臨む。この真ん中の谷を包み込むように、帯曲輪の両端からは細長い曲輪が配置され、谷を這い登る敵勢を両側から挟撃する態勢をとっている。北側の曲輪は良好に残存し、土壇や切岸が明瞭に観察できる。南側は麓の集落に帰農した松田氏末裔の方々の墓地となっている。ここから、新庄松田氏の支配化にあった平岡新庄の谷が一望でき、浦上方の出城といわれる松撫城を指呼の間に望むことができる。
本丸両側面は切り立った急斜面なので、そのまま要害地形を利用している。曲輪群は傾斜の緩やかな正面を集中的にガードするかたちで築かれている。本丸正面にあたる東側は一段の犬走がテラス状に伸び、その下にはさらに帯曲輪がおかれ、ひな壇状の三段構えになって深い谷に臨む。この真ん中の谷を包み込むように、帯曲輪の両端からは細長い曲輪が配置され、谷を這い登る敵勢を両側から挟撃する態勢をとっている。北側の曲輪は良好に残存し、土壇や切岸が明瞭に観察できる。南側は麓の集落に帰農した松田氏末裔の方々の墓地となっている。ここから、新庄松田氏の支配化にあった平岡新庄の谷が一望でき、浦上方の出城といわれる松撫城を指呼の間に望むことができる。