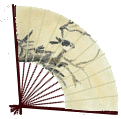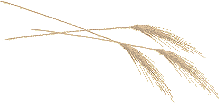 |
秋かぜのすみかへ 落穂ひろいトップページへ |
扇
(秋篠月清集 下 歌合百首) |
|
《私訳》手に慣れ親しませた夏の扇と思っていたけれど、気が付くとただ、秋風の住処だったのだな。 《他出》六百番歌合夏下七番・扇、左(女房を名乗る)。夫木抄九。《私注》良経の歌を紹介しよう、と思ったときから、最初に選ぶ歌は決まっていました。わかりやすく、リズムに渋滞がなく、良経の詩精神を端的に表しているから。もちろん、早うこのバカ猛暑にどっかいってもらいたいっていう気持ちも込めて、です^^; 建久三年(1192)…といえば、「いい国つくろー鎌倉幕府」なんですが、この年二十四歳になった良経は、歌合を企画します。良経自身を含む作者十二名に百首ずつ和歌をつくらせ、集まった計千二百首を左右六百番につがえて戦わせるという大規模な催しで、後に六百番歌合として世に知られました。今回紹介する「手にならす…」は、この歌合の際良経が詠んだ作品の一つです。 それにしても、わかりやすくてすっと入っていける歌です。私のように、国文のくせにちっとも和歌を勉強させてもらえなかった(T
T)人間でも、すんなり読める。古典文法なんて知らない、古文なんて大っ嫌いな人でも、意味をとることは出来そうです。 でも、それだけでしょうか。 良経は夏の片隅に潜む凋落の秋をみつめる。「手にならす」扇の風を切る音に、自らの内奥に巣食う秋風を、死の声を聴いているのかもしれません。 「おもへども ただ」を挟んで、上句と下句の間には大きな断絶があります。上は、私たちが普段目にすることができる世界。下は、存在してはいるのだけれど、良経のような感性の持ち主にしか、入っていけない世界。 世は夏の真っ盛り、ひとり手の中の秋を凝視する良経。何もかも見えてしまうことは、こんなに孤独で悲しい。 蛇足ながらこの歌、六百番歌合では叔父さんの慈円の「夕まぐれならす扇の風にこそ かつがつ秋は立ちはじめけれ」と対決し、判者(勝敗を判定する人)藤原俊成は慈円の方を勝にしています。好みの違いがあるから、歌合の判定ってする人も、後で読む人も判断に苦しむ。皆さんはどっちが好きですか? |
|
| 秋かぜのすみかへ 言の葉づくしへ トップページへ | |